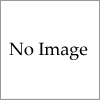
楢山節考 [VHS]
深沢七郎が中央公論新人賞をとった「楢山節考」を原作にした作品です。
で、見ていて一番気になったのは、この村人達は本当に食うのに困っているのだろうか?ということです。食い扶持を減らすため婆さまを遠くの山に捨てに行く、という棄老伝説を題材にした話にしてはそこまで村の人たちは困ってないんじゃないの?という感覚が抜けませんでした。
原作に書かれていたエピソードは忠実に描かれていて普通に見れました。あとは今村監督の脚色なんでしょうか?原作にないものもけっこうあります。
最後の、緒方拳が自分のおっかあを楢山に捨てに行き、帰り際雪が降り、そして思わずおっかあに向かって叫ぶシーンは、原作と同じく、なみだ滴ります。

楢山節考 [DVD]
深沢七郎の原作本を元に、今村昌平監督作品と木下惠介監督作品とが存在しています。但し、この2作品はかなり監督の狙い等が異なり心象が大きく異なりますので、ぜひ両作品を比べて見て頂きたいとも思いますし、またそれだけの価値もあろうかと思います。ここでは、敢えて片方しか見ないであろう方へのご参考になれば、、と思い、所感を記載してみました。●人間の本性・業・性(さが・せい)、過去の貧しい凄惨な農村の実態を本音で見つめたい場合&考えたい場合;⇒何と言っても今村昌平監督作品となります。当時の貧しすぎる奥深い農村は、余りにもリアルであり、緒形拳、坂本スミ子らの演技も光る!!但し、時に性(せい)を少々これでもか的に、あるいは少し動物・昆虫に置き換えコミカルに描き過ぎているのが悔やまれる。ところで、本の原作に感動して、親が子供と一緒に この今村昌平監督作品を見たりすると、大慌てするシーンが続出しますので要注意!これは大人が見る作品と割り切るほうが良いでしょう。逆に、子供に当り障りの無い作品として見せたい場合は、木下惠介監督となります。但し、先に本の原作を読ませておかないと、木下惠介監督はイマイチ深い理解が得られないような気もします。木下惠介監督は、はっきり言ってとてもマイルドなのです。歌舞伎的な流れの中で、背景画像も幻想的で、柔らかい御伽噺的な形、いつも根底に流れるエグイものには触れないでおこうとする優しさ(?)、、。最後に近いシーンで、同じ村のせがれが親を谷に落とした後、原本には無い、せがれも谷に落とされる一種の勧善懲悪的な付加内容には少々苦笑してしまいましたが、、。書いているうちに、今村昌平監督作品の良さの方が目立つ記載になってしまった感がありますが、ご参考にしてください。

笛吹川 (講談社文芸文庫)
甲府と石和の間を流れる笛吹川の土手の小屋に住む一家を六代にわたって描いた長編。「お屋形様」(武田家)との関わりによって、家族が次々に死に、殺される顛末が描かれているのだけれど、深沢氏の筆致は淡々としていて、心理や感情を排して傍観者として見つめている。そのヒューマニズム臭くないところがとても好きだ。生きていく上で生じるいざこざやズレを人間の大きな流れの中にある「営み」として無言のうちに肯定されているようで緩やかな気持ちになる。

楢山節考 [DVD]
僕は皆さんのように良い文章(レビュー)は書けないけれど、この映画を鑑賞して
思った事を書いてみます。
映画自体はまぎれもなく日本映画界傑作の中の一つであると思いますし、
主演の緒形拳をはじめとする俳優の名演に惹きつけられると思います。
貧しさと子孫を残していく為に姥捨てという行為が昔、行われていた事、
進んで山へ行こうとする母親とそれに葛藤する息子の心情もひしひしと
伝わってきます。
寒村の貧しい村に生きる人間の生き様と貪欲さ、性などを綺麗に見せず
有りのままであろう姿で描写されています。またラストも当然ハッピーエンドではなく
切なさが残る終わり方です。エロティックなシーンがあるので子供とは見れない作品で
すが、この飽食時代に育った自分を含めた世代にとっては豊かさ貧しさを再考させてく
れる映画であると思います。

楢山節考 (新潮文庫)
短篇4作が収録されているが、何度も何度も繰り返し読んでいるのは「楢山節考」。読み方はいつも異なっていたが、いつ読んでも思うのは、何度読んでも、どんな読み方をしても圧倒されてしまう小説ということ。
最初に読んだのは高校生の頃。今から20年以上前のことだ。
ただ、ひたすら恐ろしい小説だと思った。辰平が母親のおりんを背負って山を登る途中の描写、辰平がおりんを岩陰に捨てて山を下り始めたときの描写(ほんの数行の文章だが)、辰平が山を降りる途中で見た銭屋の又やんが捨てられる時の描写など終盤はとにかく恐ろしかった。カラスの鳴き声が耳から離れなかった。
解説に倣ってアンチ・ヒューマニズムの小説として読んだ(読もうとした)こともある。
日本のムラ社会の閉鎖性を描いた小説として読んだ(読もうとした)こともある。
一歩進んで、村人が「神」と信ずるムラ社会の掟に縛られる哀れな姿を描いた小説として読んだ(読もうとした)こともある。
ただ、こう読んでしまえば、おりんを山に捨てながら一旦は彼女のところへ引き返した辰平も結局のところはムラの掟に縛られている哀れな人物と捉えることになってしまうのだが・・・。
単純な親子愛を描いた作品として読んだ(読もうとした)こともあるが、お涙頂戴ものとしては読めなかった。舞台設定等がそれを許さない部分もあるが、それ以上に、この作品全体に漂っている、著者の人生に対するある種の諦観みたいなものが感じられるからだと思った。
著者深沢七郎がおりんに「神」を見ているのだろうか、と考えたこともある。ムラの掟に何も疑問を持たず嬉々として山へ向かう準備を進めるおりんの姿は滑稽ですらあるがその中に強さを感じる取ることもできるし、山の岩陰に捨てられたおりんが一身に念仏を唱える姿、そして引き返してきた辰平に手を振りながら無言で「山を降りろ」と訴える姿は神々しささえ感じさせるからだ。
何年か振りに読んでみたが、結局のところどう読めばいいのかという自分なりの結論は出せなかった。これからも出せないような気がする。







